気づきにくい“心のサイン
「うちの子、最近イライラしやすい?」「友達とうまく遊べていない?」——そんな悩みを抱える保護者は少なくありません
実はこれらの行動の裏に、聞こえのトラブルが潜んでいることがあります。
難聴は視覚的に分かりにくく、本人も周囲も気づかないまま “聞こえづらさ” が心や行動に影響を及ぼすケースがあるのです。
なぜ聞こえが心を左右するのか
言葉を聞き取り、相手に伝える——この“当たり前”のプロセスがスムーズにいかないと、子どもは社会的なやり取りでストレスを抱えがちです。
乳幼児期に難聴を放置すると、言語発達が遅れ、学校生活でのコミュニケーションに壁が生じます。失敗経験の積み重ねは自尊心を下げ、攻撃的な行動や不安・抑うつへとつながることも。

だからこそ日本でも新生児聴覚スクリーニングが導入され、早期介入(補聴器・人工内耳・ことばの訓練)が推奨されているのです。
しかし「機器を装着すれば安心」とは限りません。補聴後も心理的サポートを続ける必要があるか——そこに光を当てたのが今回の研究です。
研究内容のあらまし:エジプト発の最新データ
2025年5月に発表されたエジプト・ミニア大学の研究では、4〜17歳の難聴児127名(補聴器71名・人工内耳56名)を対象に、保護者版“強みと困りごと質問票(SDQ)”で感情・行動面を評価しました。
調査項目は「情緒的問題」「行動上の問題(乱暴・反抗的行動)」「多動性/不注意問題」「友達関係の問題」「社会性」の5領域。
さらに 難聴の重症度、補聴までの遅れ、年齢層なども分析して「どの子がどんな困りごとを抱えやすいか」を探りました。
結果と私たちの生活へのヒント
重症度との意外な関係
最も行動面のトラブル(反抗・乱暴など)が多かったのは、重度より“中等度”の難聴児(約60%)でした。聞こえが少し残っている分、周囲に見落とされやすく、診断・支援が遅れがちなことが一因と考えられています。
年齢で変わる困りごと
小学校入学期(6–12歳)は86%が“友達関係の悩み”を抱え、思春期(12–18歳)は約67%が“不安・抑うつ”など内面の問題を報告しました。学校・部活動など社会的要求が増えるタイミングで支援内容を変える必要があります。
機器の種類や装着側では差が出ず
補聴器でも人工内耳でも、心理面のスコアに有意差はありませんでした。「機器を装着すればOK」ではなく、装着後のコミュニケーション練習と心理的サポートが鍵だと示唆されます。
生活へのヒント
- 耳のチェックは“ことばの遅れ”より前に:1歳未満の聴覚スクリーニングと専門医受診を。
- 学校生活の節目で“心の健診”:入学前・思春期に心理評価をセットで行う。
- 家庭でできるサポート:アイコンタクト→短い文で話す→褒めて自己肯定感を高める。
- 医療機関との連携:補聴専門外来+心理師・言語聴覚士のチーム支援を早期に始める。
結論:
難聴の子どもは、聞こえにくさが原因で行動や感情の問題を抱えることがあります。補聴器だけでなく心のケアも重要。早期発見と適切な支援が、子どもの成長と笑顔を守ります。
※本記事は最新研究を分かりやすく解説したものであり、診断・治療は専門医へご相談ください。
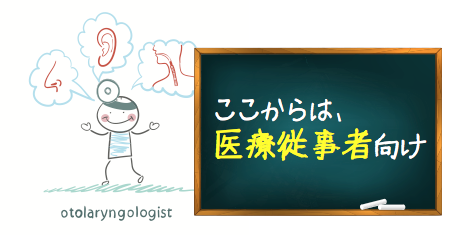
今回参考にした論文は、
Fahim DFM, et al. Emotional and behavioral problems in children and adolescents with hearing impairment. BMC Pediatr. 2025;25:369.
DOI:10.1186/s12887-025-05696-4
です。
Research Question:
補聴器・人工内耳装用児における難聴重症度・年齢層が感情・行動問題(SDQ)の発現率に及ぼす影響は?
Methods:
デザイン:
横断的記述研究
サンプル:
127名(エジプト単施設, 4–17歳)
内訳:補聴器 71名, 人工内耳 56名
主要アウトカム:
SDQ(strength difficulty questionnaire) 5領域(親記入)
・emotional problems
・conduct problems
・hyperactivity/Inattention problem
・peer relationship problems
・prosocial behavior
解析:
χ²/ Fisher, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney
多変量線形回帰(調整因子: 年齢, 診断年齢, 性別, HL重症度ほか)
Results:
- 難聴の程度別
- 行動上の問題: 中等度難聴 60.6% vs 重度難聴 52.4% vs 最重度難聴 48%(p<0.05)
- 年代別
- 友達関係の問題: early childhood 6–12歳 86%(p = 0.003)
- 情緒的問題: late childhood 12–18歳 66.6%(p = 0.023)
- 装置種別・装着側によるSDQの差はなし
- 多変量線形回帰では、診断年齢の遅れと総SDQスコアが有意に関連していた。
Conclusion & Implication:
- 著者結論: 補聴器や人工内耳の早期装用後も、感情・行動面の問題は残ることがあり、とくに診断の遅れや年齢に特有の課題が影響する。
- 臨床応用: 聴覚リハビリと並行してSDQによる心理評価を定期的に行い、入学期や思春期には支援を強化すべき。診断の遅れが懸念される家庭への啓発も重要。
- リサーチギャップ: 縦断的研究や介入効果の検証が今後の課題。







