外来で患者さんを診ていると、耳鼻咽喉科という科の特徴かもしれませんが、比較的元気な方が多く受診されます。今は高齢化社会ですので、お元気な80歳代、90歳代の方が来られます。(もちろん耳や鼻、のどの調子が悪くてこられているのですが…。)
そのようなかくしゃくとした方々を診察しながら、「私も元気に長生きしたいものだな」とつくづく思います。
長生きの秘訣は?
長生きの秘訣は何でしょうか?
まず思いつくのは、バランスの良い食事。そして、適度な運動習慣や睡眠ではないでしょうか。もちろんそれらは大事なことで、患者さんにもいつもお勧めしています(「お前はどうなんだ」という声なき声を聞きながらw)。
食事や運動習慣、睡眠といった身体に対する取り組みも大事ですが、心に対する取り組みも大事だと言われています。
心に対する取り組みの中でも、人生の目的意識を強く持つことが注目されていて、人生に目的意識を持つことは、身体的・精神的な健康状態の改善につながり、生活の質を高めることを示す研究が多く発表されています。
人生の目的意識の大切さ
今回とりあげた論文では、人生の目的について、“a self-organizing life aim that stimulates goals, promotes healthy behaviors, and gives meaning to life”(直訳:目標を刺激し、健康的な行動を促進し、人生に意味を与える自己組織化された人生の目的)と定義されています。ちょっと難しい定義ですね。医学の学術論文ですからね。
もう少し平易な言葉で一般化してみましょう。多くの人に読まれている『7つの習慣』の中には、第2番目の習慣として次のように書かれています。
第2の習慣「終わりを思い描くことから始める」は生活のさまざまな場面やライフステージに当てはまる習慣だが、もっとも基本的なレベルで言うなら、人生におけるすべての行動を測る尺度、基準として、自分の人生の最後を思い描き、それを念頭に置いて今日という一日を始めることである。そうすれば、あなたにとって本当に大切なことに沿って、今日の生き方を、明日の生き方を、来週の生き方を、来月の生き方を計画することができる。人生が終わる時をありありと思い描き、意識することによって、あなたにとってもっとも重要な基準に反しない行動をとり、あなたの人生のビジョンを有意義なかたちで実現できるようになる。
終わりを思い描くことから始めるというのは、目的地をはっきりさせてから一歩を踏み出すことである。目的地がわかれば、現在いる場所のこともわかるから、正しい方向へ進んでいくことができる。
『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』(スティーブン R コヴィー 著:キングベアー出版)より
人生の行き先を思い描いて意識して、人生のビジョンをはっきりさせるということですね。
人生の目的意識は健康に良い影響を与えるのか?
今まで行われてきたいろいろな研究では、目的意識のある人や生きがいのある人は、健康的な行動をとり、睡眠障害が改善したり、脳卒中の発症率が低下したり、脳卒中後の生活の質が向上したり、うつ病の状態が改善したり、糖尿病の健康状態が改善したりするなど、いろいろな効果が報告されています。
また、目的意識や生きがいがあり幸福感が強いと、炎症を引き起こす遺伝子の発現が低下することを示した研究もあります。炎症性マーカーであるCRPや、IL-6などのサイトカインの上昇は死亡率の上昇と関連しているという報告もあるので、関連性があるのかもしれません。もちろん、まだはっきりとしたことは解明されていませんが…。
下に示した論文は、アメリカの50歳代以上のおよそ7000人を調べた研究結果です。それによると、人生の目的意識が高い人は死亡するリスクが有意に低く、長生きする傾向にあることが示されました。人生の目的意識が最も高い人達と最も低い人達とを比較すると、死亡するリスクは2.5倍ほど違うのだそうです。
コロナ、コロナで生きづらいことばかりのご時世ですが、将来へのビジョンを持って前向きに生きていきたいですね。
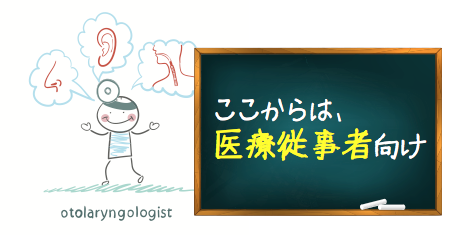
今回参考にした論文は、
Alimujiang A, et al. Association Between Life Purpose and Mortality Among US Adults Older Than 50 Years. JAMA Netw Open. 2019; 2(5): e194270.
doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.4270.
です。
Research Question:
人生に目的意識を持つことと、死亡率とに関連があるかを評価する。
方法:
デザイン:
前向きコホート研究
対象:
Health and Retirement Study※ の参加者から無作為に抽出され
2006年に心理学的質問票に回答した8,419名
※アメリカの51〜61歳の成人を対象とした全国規模のコホート
調査内容:
修正Ryff and Keyes Scales of Psychological Well-being質問票を用いて
人生の目的意識を調査した。
項目は7項目。それぞれ6段階のリッカート尺度で評価。
スコアが高いほど意識が高いことを示す。
今回は、平均スコアを5つのカテゴリー(1.00-2.99、3.00-3.99、
4.00-4.99、5.00-5.99、6.00)に分類して評価した。
評価項目:
2006〜2010年にかけての全死亡率と原因別死亡率を
重み付けCox比例ハザードモデルで評価した。共変量は原著参照のこと。
結果:
- 8,419名のうち、データが不十分であったり追跡できなかった参加者を除外したところ、最終的に解析対象となったのは6,985名であった。
- 4,016人(57.5%)が女性であり、全参加者の平均年齢±標準偏差は68.6±9.8歳。
- 死亡したのは776名で、調査開始からの平均生存期間±標準偏差は31.21±15.42カ月(範囲:1~71カ月)であった。死因の上位4位は、心血管および血液疾患(297名)、悪性腫瘍(208名)、呼吸器疾患(108名)、消化器疾患(86名)であった。
- 人生の目的意識の度合いは、全死亡率と有意に関連していた(ハザード比 2.43 [1.57-3.75]、意識が最も低いカテゴリーの人と最も高いカテゴリーの人を比較)
- 逆の因果関係(死期が近くなると人生の目的意識が低下する)の可能性を探るため感度分析を行った。追跡期間の最初の1年間に死亡した参加者を除外しても、人生の目的意識と死亡リスクとの関連は同様の結果となった(ハザード比 2.24 [1.44-3.50])。また、調査開始時に慢性疾患に罹患していた参加者を除外しても、依然として関連性が認められた。
- 人生の目的意識の度合いと原因別死亡率との有意な関連もいくつか認められた。(心血管および血液疾患:ハザード比 2.66 [1.62-4.38]など)。
- []内は95%信頼区間。
結論:
人生の目的意識の強さが、死亡率の低下と関連することが示された。目的を持って生きることは、健康上のメリットがあるかもしれない。
今後の研究では、人生の目的意識へ介入することが死亡率を含む健康アウトカムに関連するかを評価することが重要である。また、人生の目的意識が健康アウトカムに影響を与える可能性のある生物学的メカニズムを解明することも重要である。







