新型コロナ感染症(COVID-19)の蔓延は、なかなかおさまりませんね。治療薬やワクチンの開発もこの2〜3年の間にどんどん進んできています。
かかった後の治療ももちろん大事ですが、かからないように予防することも大事です。何かいい予防法はないでしょうか?
第一には、マスクや手洗いなどの感染対策であることは間違いありませんが、「他にも何かあるといいな」と考えてみたりします。
今回の記事では、まだ予防法のヒントになるかもしれないという段階の情報ではありますが、最近日本発で出された論文を紹介したいと思います。
慢性上咽頭炎と上咽頭擦過療法(EAT)
突然ですが、慢性上咽頭炎という病気をご存じでしょうか。以前、このブログでもご紹介しましたので、ご存じない方は、こちらをごらんください。
この記事でも紹介していますが、慢性上咽頭炎の治療に上咽頭擦過療法 (EAT) というのがあります。Bスポット療法とも言われています。ちなみにBスポットの”B”は鼻咽腔の”B”なのだそうです。めっちゃ日本語です(^^;)。
EATというのは、塩化亜鉛という薬をつけた綿棒で、上咽頭(鼻の奥)の粘膜をこすって、炎症を落ち着かせていく治療です。
この治療がCOVID-19の予防につながるかもしれないというのが、今回の内容です。
新型コロナの感染メカニズム
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染はどのように起こるのでしょうか。
新型コロナウイルスが、鼻やのどの粘膜にやってくると、粘膜の上にあるACE2という受容体にくっつきます。そして、TMPRSS2というタンパク質を分解する酵素によって分解され、粘膜細胞の中に取り込まれていきます。もっと詳しい説明は、下のアイコンをクリックすると図が出てきます。
ですから、新型コロナウイルスの感染にはACE2とTMPRSS2が必須であり、カギとなる分子ということです。
EATで感染のカギとなる分子が減る
下に示した論文は、慢性上咽頭炎の患者さんから粘膜を採取して、EATを受けていない患者さんとEATを受けた患者さんとを比較した研究です。
それによると、EATを受けた患者さんの粘膜では受けていない患者さんと比較して、新型コロナウイルス感染でカギとなる分子であるACE2とTMPRSS2が2つとも少なくなっていることが分かりました。
つまり、EATを受けた患者さんの粘膜では、新型コロナウイルス感染が起こりづらくなっているかもしれないということです。
ここで注意が必要なのは、この情報を聞いてすぐさまEATを受けようと思わないことです。
今回の結果は、あくまでEATを行った上咽頭の粘膜で感染のカギとなる分子が減ったということを示しているだけで、実際にEATを行ったらCOVID-19にかかりにくくなるかはわかっていません。実際に、EATをやっている人とやっていない人でCOVID-19の感染率が異なるかどうかを調べなければ本当のところはわかりません。
また、新型コロナウイルスが感染する場所は上咽頭だけではなく、他の鼻やのどの粘膜もあることを考えなければなりません。
それを踏まえた上で、EATの可能性を個人的には期待したいと思います。上咽頭はまだまだわからないことが多い場所だと思います。
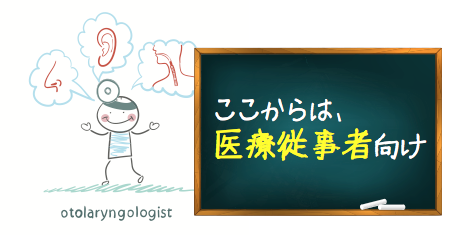
今回参考にした論文は、
Nishi K, et al. Epipharyngeal Abrasive Therapy Down-regulates the Expression of SARS-CoV-2 Entry Factors ACE2 and TMPRSS2. In Vivo. 2022; 36(1): 371-374.
doi: 10.21873/invivo.12712.
です。
Research Question:
上咽頭擦過療法(EAT)によって上咽頭粘膜のACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) やTMPRSS2 (transmembrane protease, serine 2) の発現が減少するか。
方法:
対象:
慢性上咽頭炎患者から生検された咽頭上皮
(2021年7月〜2021年8月に採取)
比較する群:
非EAT群:EATを受けていない患者 7名
EAT群:EATを1カ月以上受けている患者 11名
評価項目:
咽頭粘膜上皮に発現するACE2とTMPRSS2の発現量を比較
(mRNA in situ hybridizationと免疫組織化学で比較)
結果:
- 非EAT群 7名の平均年齢は53.3±15.3歳、EAT群 11名の平均年齢は64.4±11.9歳であった。
- 免疫組織化学のIHCスコアは以下の通り。
- ACE2:非EAT群はEAT群に比べて発現が3.40倍高かった(p=0.0208)。
- TMPRSS2:非EAT群はEAT群に比べて発現が1.81倍高かった(p=0.0244)。
- 組織学的には、非EAT群の粘膜は線毛上皮で構成されていたが、EAT群では扁平上皮化生が認められた。
- 免疫組織化学およびmRNA in situ hybridizationの結果、EAT群の扁平上皮化生の領域ではACE2およびTMPRSS2は、蛋白においてもmRNAにおいても発現が認められなかった。
結論:
EATは上咽頭粘膜のACE2やTMPRSS2の発現を抑制するため、上咽頭におけるSARS-CoV-2感染を抑制できるかもしれない。







